昨年末から府中市美術館で開催されている「諏訪敦 眼窩裏の火事」展。
不勉強ながら諏訪敦についてほとんど知らなかったのですが、Twitterでやけに絶賛コメントが目についたので、徐々に気になり始め、ようやく行ってきました。
展示構成

展覧会は3章で構成されている。「第1章:棄民」「第2章:静物画について」「第3章:わたしたちはふたたびであう」。一般的に章のタイトルは名詞なら名詞、体言止めなら体言止め、文章なら文章と、体裁を統一させるものだ。なぜ敢えてこのようなタイトルにしたのだろうか。展示を見ればその意図するところがわかるのだろうか。
第1章:棄民
第1章は、自身の父親の死を機に、その母親である祖母が満州で亡くなった事実を知った諏訪が、彼女が生きた証を求めて満州まで取材した《棄民》シリーズを中心に構成されている。この章では、父・祖母という肉親をテーマにした作品が並ぶ。
展示室に入ると、まず目に入るのが壁の高いところに掲げられた《棄民》。着物を着た若い女性が幼い少年を膝に抱えた肖像画。西洋の聖母子像のような構図だが、女性の顔は部分的に頭蓋骨が見えるように描かれ、少年の顔も一部が判然としない。まるで写真を火につけた時に燃えるような光が、彼らの顔の前に現れている。
幽霊画のような寒々しい肖像画が高々と掲げられた空間の中で、彼女・彼に見守れながら(あるいは見張られながら)「諏訪家の物語」が始まる。この物語は「死」から始まる。
会場では、まず父親が病床で昏睡している姿を描いた大画面の《father》、そして臨終の姿を描いたスケッチが並ぶ。生々しいまでの「死」。絵だと分かっているのに凝視するのが躊躇われてしまう。もはや「生」を終えて、見られることに抵抗できない相手を凝視する一方的な状態に、逆にこちら側が耐えられなくなってしまう。
その死に端を発して画家は、父親がかつて家族と共に満州にいたこと、ソ連侵攻によって難民収容所に留められ、そこで祖母と叔父が栄養失調と発疹チフスで亡くなったことを知る。そこから、彼らの人生は何だったのかを追い求め、画家は満州に赴き、取材を重ねる。
その集大成となる作品が《HARBIN 1945 WINTER》だ。痩せた女性が雪景色の中で息絶えている。肋骨が見えるほどに痩せこけ、体には痛々しい血の跡もある。故郷から遠く離れた土地で、病気になって死んだ祖母の人生をたどるように、この絵は描かれている。
会場では、《HARBIN 1945 WINTER》の後に描かれた《依代》が、前者と対になるように飾られている。《依代》では、女性はふくよかな肉付きを取り戻し、”きれい”な姿で、まるで眠る裸婦像のように描かれている。画面の中で痩せて死んでいった女性の尊厳を取り戻すために描かれたという。
この解説を知らなければ、むしろ「きれい」な状態から「死んでいく(朽ちていく)」という、九相図(死んでから白骨化するまでの様子を9つの段階に分けて描く画題)のように思ったことだろう。展示の動線では先に《依代》を見るのが自然の流れのように思えるので、そうした構想も含んでいたのかもしれない。
「きれいな体の女性」が「痩せこけて死ぬ」。そしてまた展示室を一周して戻る時に、「美しい体を尊厳を取り戻す」。1枚の絵の中で女性の死を描き、展示空間を使って、生と死の輪廻を表現しようとしていたのではないだろうか。
第2章:静物画について
第2章は、コロナ禍で始まったプロジェクトで生まれた静物画が並ぶ。ここでは高橋由一の《豆腐》やオランダのヴァニタス画など、西洋の古典絵画、近代日本の洋画など過去の様式や作品を換骨奪胎して、”諏訪式静物画”を制作する。
写実的に描くからこその静謐さ、シュールさ
展示室の解説では、前述の通り高橋由一やヴァニタス画などが挙げられていたが、個人的にはフェルメール、あるいはモランディを思い出す。フェルメールは、その精緻さ、写実性の高さ、あるいは光の反射への関心ゆえに、モランディは、モチーフの並べ方や構図、全体に灰色がかった画面の印象ゆえに。
これらの作品に比べたら、同じ静物画でもセザンヌやゴッホなどは騒々しい。それは絵筆のタッチによるところも大きいし、絶妙にモチーフの配置を組み合わせる構図、視点も大きい。
そう思うと、諏訪の作品は、画面を構築するあらゆるファクターにおいて、”より静かに感じる”方法を選んでいった結果のように感じる。諏訪の静物画は、小さなガラスのグラスとといった小ぶりなモチーフをほぼ真横から見る視点で描かれている。小さな小さなせかいーーそのミクロな視点と、精緻で画家の存在を忘れさせるほどに写実的な描写によって、画面は独特の静けさに満ちている。
そしてなぜかそれがシュールにさえ思えてしまうのはなぜだろう。仙厓による禅画《〇△□》を主題にして、〇をガラスの器の口縁、△を筍、□を豆腐に置き換えた《まるさんかくしかく》など、禅僧が墨で一気呵成に筆をふるってあらゆる事象から本質を抽出し表した主題を、再び器、筍、豆腐という具象に置き換えているのは、皮肉と言おうか、「空即是色 色即是空」と言おうか…。
「”ない”のに”ある”」の共有ー画家の眼の追体験
そして、その”諏訪式静物画”の展覧会のタイトルにもなった《眼窩裏の火事》も展示されている。静物画には、モチーフを遮るような光や陽炎のような揺らめきがしばしば描かれている。これは画家自身が患っている閃輝暗点(せんきあんてん)という病気の症状で、閃光のような光が現れる。この実在しないけれども、確実に画家の眼にだけは映っている”光(揺らめき)”を「眼窩裏の火事」と表現しているのだろう。
この「ない」のに「ある」感覚、目をこすっても症状が治まらず、自分ではどうしようもないもどかしさ、実にわかる。閃輝暗点ではないが、私も飛蚊症で左目にずっと黒い糸くずがあるように見える。眼科で自然に治癒することはないと言われた時の軽い絶望。『もののけ姫』で主人公のアシタカが「曇りなき眼で見定める」という台詞を言うシーンがあるが、「あぁ私はもう”曇りなき眼”で見ることはできないのだな」と思ったものだ。
そう思うと、展示室に飾られている静物画は、強制的に諏訪の見ている世界を鑑賞者に追体験させることになる。自分の眼で見ているはずの鑑賞者に対して、ちゃんと見たいのに見えないもどかしさや「ないのにある」という現象を共有させる。
画家の眼球の奥で起きた”眼窩裏の火事”は、鑑賞者の眼にまで延焼しているのだ。
写実性の高い諏訪の作品だからこそ、一層この「見えないこと」が強調されているのも面白い(人が患っている症状を面白いと言ってしまうのは憚られるが)。
「追体験」という意味では、第1章の《棄民》と通じる部分もあるだろう。棄民シリーズでは時間の蓄積(経過)という追体験の仕方であったが、ここでは症状、つまり身体の追体験として。
第3章:わたしたちはふたたびであう
第3章は、これまでに画家が手掛けてきた肖像画を取り上げる。依頼を受けたモデルを綿密に取材し、時間を重ねて制作していく諏訪の仕事は、時にモデル本人の死によって途絶えることもある。死によって二度と会うことができなってしまっても、取材を通して描く対象と積み重ねてきた時間は決して失われることはない。そして諏訪の作品は、時間を重ねる中で更新されていく。画家の手元に残る絵をてがかりに、彼らとふたたびであい、その再会を鑑賞者もまたその出会いに立ち会うことができる。
会場では、ジャーナリストの佐藤和孝氏の30代、40代の時の肖像画や、彼の妻である山本美香氏、あるいは日本人と外国人の同性カップルなどの肖像画が並ぶ。
圧巻だったのは、舞踏家・大野一雄の晩年の姿を描いた一連の作品と、その大野に触発されたパフォーマー・川口隆夫の姿を描いた作品群だ。広い展示室の中、入り口の真向いに掲げられているのは、大野が100歳となって寝たきりになった姿を描いた《大野一雄》。第1章の病床に伏せる父親の姿と同じく、ここでも物語は「死」から始まる。
その作品に向って左手側の壁には90歳の頃を描いた《大野一雄立像》が展示されている。鑑賞者はまず《大野一雄》で、老いた舞踏家の晩年、寝たきりとなった事実に向き合う。見続けるのが苦しくなるほどの弱弱しく無抵抗な姿。そして左を向けば《大野一雄立像》が映る。90代の大野は立って歩くことはできていたようだが、痩せて皮膚がたるみ、いかにも”老人”という体つきだ。画家を出迎えた時の格好なのか、下着一枚でやや猫背気味で、舞踏家という説明がなければしがない老人にしか見えず、初めて大野一雄という人物を知った私には、彼の舞踏家としての姿が想像できない。
一方で、《大野一雄立像》と対になるように、向かいの壁には《Mimesis》が掲げられている。これはパフォーマーの川口隆夫が、大野一雄に触発され、彼の踊る姿を模倣した姿を描いた作品で、まるでコマ送りか残像のように、幾つもの腕や顔が重層的に描かれている。彼の踊る時間そのものが絵の中に閉じ込められているかのようだ。
人は死ねば、肉体と共にその人の生きた時間も失われていくように感じられる。しかし、こうした諏訪の絵画、川口のパフォーマンスによって、大野一雄という一人の舞踏家がずっと生き続けていくことを感じる。特に《Mimesis》では、川口の身体の中に「大野一雄」が入り込む。
この作品を観た時、ふと能の『鷺』という演目を思い出した。帝の命で白鷺が御所の池に降り立ち舞を披露して、再び立ち去るという筋だが、この演目は若い頃と老人となってからでしか演じることができないという。子供や老人は神に近い神聖な存在として考えるからで、私はここに舞台に立つ者の輪廻を想った。
※『鷺』についてはnoteで詳しく書いているのでこちらもご参照ください。
肉体を超えて、時に他者の肉体をも借りて生き続ける。「一個体」の記憶が「他者」に伝播し続ける、廻り続ける。あるいは木々や草花の芽吹き、花開き、枯れ、再び新しい芽が生える、生生流転のイメージも沸き起こる。人間の生もまた、その循環の一つなのだと思った。
そのことが救いになるのか、無常になるのかはわからない。どちらとも言えるだろう。ただそれを認めようとも拒もうとも、そうなのだ。生きることも死ぬことも、どちらも等しく、大きな流転の中で起こることなのだ。
展示を見終えて
事前に「大充実の展覧会だった」というコメントを多く見ていたので、気合を入れて観に行ったのだが、作品点数が多いわけではないので、30分もあれば十分見ることができる規模だった。
しかし、展示作品の数や鑑賞時間が充足感と比例するとは限らない。たとえ30分でも、体の中に確かに静かに満ちてくる何かがあった。鑑賞時間が短かったのは、おそらく私が《father》や《大野一雄》の作品のように、老いた老人の姿の生々しさに耐えられずにいたからで、それは諏訪の真に迫る描写の賜物と言える。
ひとつ断っておきたいのは、その”耐えられなさ”は私自身が人の死に向き合うことを恐れるからで、決して諏訪の作品がグロテスク、あるいは死をことさら強調する悪趣味なものだからではない。むしろ彼の写実性は「敬虔」な振る舞いのように思えた。
私の体に満ちた”何か”とは、出会いだったのかもしれない。一人の人間のちいさなちいさな人生を、画家の眼を通して繊細に緻密にたどっていく。その出会いが、彼らの生きた時間が、私の体に染み入ってきたのかもしれない。
カフェの展覧会限定メニュー「薬膳紅鍋プレート」もおすすめ

美術館併設のカフェ「府中之森珈琲店」では、展覧会限定メニューの薬膳火鍋「紅鍋」ランチプレートも。実はこれが食べたくてお昼を狙って美術館に着くようにした。
展覧会名に「火事」がつくし、見た目も辛そう…と思いきや、薬膳スープはあまり辛みはなく、むしろしみじみ体に浸透していくような深い味わいのあるスープ。牛筋のお肉もしっかり煮込まれていて柔らかくボリューム感もあり。
展示を見る前に食べたので、食べている最中は「おいしい」という感想だったが、後から考えたら、薬膳スープの染み入る深い味わいは確かに展覧会にピッタリだと思う。「火事=ホット(辛い)」に安直に置き換えず、体の内側から沸々と湧いてくるような熱さを求めた味は、展覧会限定メニューとして非常に完成度が高いと思った。
本当は展覧会を見終わった後に、もう一度カフェに入って、名物のバスクチーズケーキも試そうかなと思ったけど、腹持ちが良くてスイーツは断念。バスクチーズケーキは次回展の時にリベンジしよう!
展覧会概要
会期:2022年12月17日(土)~2023年2月26日(日)
会場:府中市美術館
開館時間:午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)
休館日:月曜日
入館料:一般 700円、高校・大学生 350円、小・中学生 150円
※団体料金など各種割引などはHPをご参照ください
展覧会HP:https://www.city.fuchu.tokyo.jp/art/tenrankai/kikakuten/2022_SUWA_Atsushi_exhibition.html

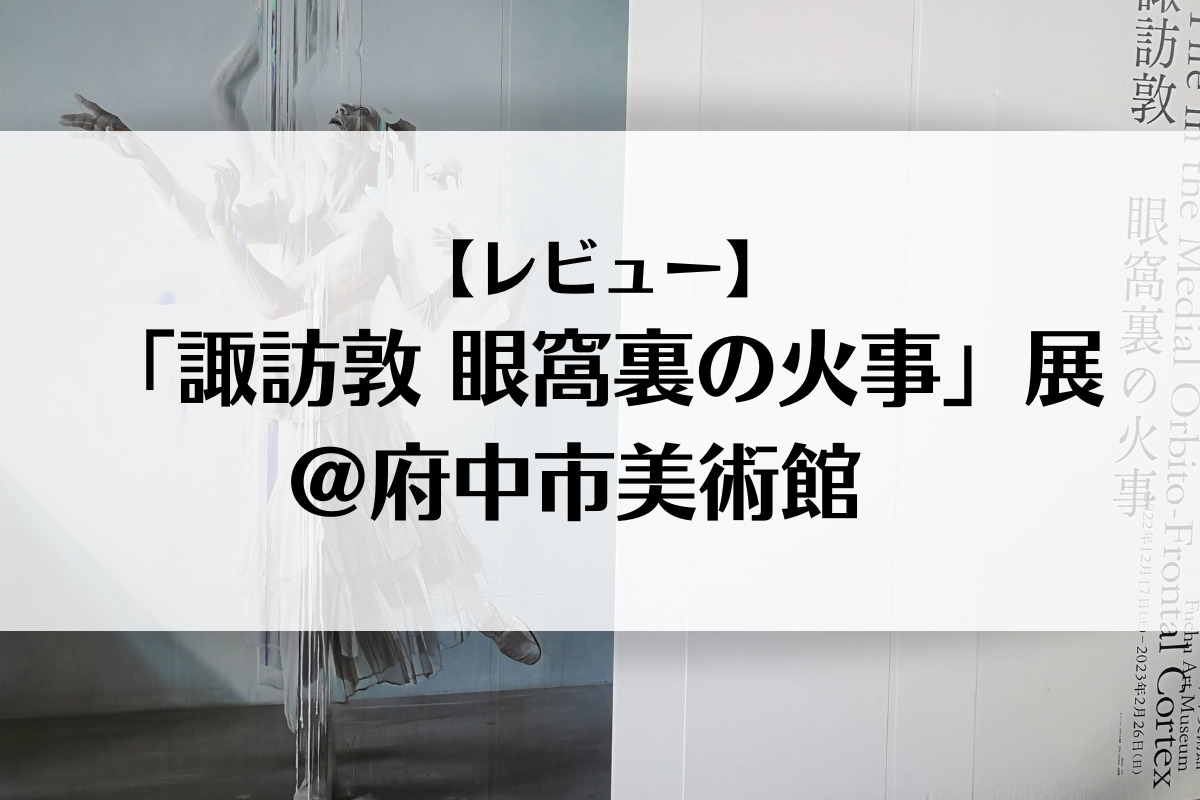
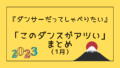

コメント