書籍情報
- 書名:未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀
- 著者:岡田利規
- 出版社:河出書房新社
- ジャンル:現代演劇・戯曲・社会批評
本書を手に取った理由
本作は同名の舞台が2020年に行われる予定だったが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。翌年上演されたのだが、その時には行くことが叶わず残念に思っていたが、2026年に第2弾が上演されると発表された。その第2弾の舞台にs**t kingzのOguriさんが主演すると知り、予習もかねて本書を手にした。
概要
本書には大きく2つの戯曲が収録されている。1つは『NO THEATER』、もう1つが表題の『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』だ。
『NO THEATER』は、ドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピーレにて、レパートリー作品として発表された作品で2018年には京都でも上演された。岡田にとって最初の「能」のフォーマットを用いた舞台。
そして、それに続いて制作されたのが『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』だ。『挫波』と『敦賀』はそれぞれ独立した物語で相互関係はない。2演目の能舞台を見るようなものと考えていい。
感想
本書の第一印象は「思っていたより、がっつり”能”だな」ということ。シテ、ワキという登場人物や、前シテ(後シテ)、そして後シテが幽霊なり怪物なり、この世のものではない者という構成をなぞらえるだけかと思ったら、詞章(台詞)の構成までも古典的な謡曲のフォーマットになぞらえている。
しかし、だからこそ活字だけでは、現代の言葉と謡曲ならではの構成(同じ詞章を2回繰り返すなど)やリズムが掴みづらく、どのように読めばいいのか分からなかった。これは私がなまじ謡の節回しを知っているからこそ起こるストレスなのかもしれない。能を知らない人が読んでも読みづらく感じるのかは分からないが、ともかく実際の舞台(演者の台詞ないし謡)を見ないと、この台詞が良いのかどうかも分からない。
なので実際の舞台を見ずに、本書で上演作品の良さを理解しようとするのは、かなり難易度が高いと思う。もちろん『未練の幽霊と怪物』という作品が、どういう思いから端を発して生まれたのか。どういう構成になっているのか、その背景や岡田の狙いを知る上では十分面白い内容だ。
細かなあらすじに触れずに感想を言うと、能のフォーマットを用いた演劇として『NO THEATER』から『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』で、かなり洗練されている。後シテの設定の意外性、物語の普遍性、彼らが語る言葉も、後者の方がよりスッと入ってくる。これが第2弾で同様のフォーマットにならうのか、さらに展開されて(崩されて)いくのか、どうなるか期待したい。
印象に残った言葉
能は役になり切らない
能の演者は、役になろうとしていない。彼らは役になるのではなく、役を呼び寄せている。
「前口上(まえがき)」の中で岡田が語る言葉だが、能という演劇の特殊性を端的に示している。ここでは、演劇の”演劇らしさ”、つまり役者が声を張り、日常生活ではほとんど見ないようなテンション、台詞回し、掛け合いなど、舞台上で”演劇だから”という前提で成立しているように見える光景に対して、一定数の人が示す拒否反応(こっ恥ずかしさ)(本文中では「演劇アレルギー」と称す)が能にはないという。
その理由として、上記の一節がある。この指摘にはハッとさせられた。例えば歌舞伎と能を比べても、どちらも男性が女性の役を演じる時があるが、歌舞伎が「女性」になり切るために声色を地声から変えているのに対し、能ではほとんど変えない。その演者の声そのままだ(多少役柄によってトーンはかえることはあるが)。その違いだけをもってしても、能の「役になるのではなく、呼び寄せる」という表現が的を得ている。
そして、その役柄も夢幻能においては、亡くなった武士、子、女(幽霊)、〇〇の精、神、鬼(怪物)と、圧倒的に現世を生きる人間ではない者が多い。そうした「声なき者の声を聴く」のが「能」とも言える。その本質を言い得た言葉で感服した。
能のフォーマットは政治的
舞台上で幽霊が自分の詩について語るのを劇場に集まった観客が見る、という能の上演のフォーマットには、すぐれて政治的になり得るポテンシャルがある。
「後口上(あとがき)」に書かれている言葉だが、この言葉にもハッとさせられた。古典の能を見ている時には意識したことなかったが、確かに源平合戦で敗れた者などかなり政治的だ。この世に何かしらの未練を残した幽霊と怪物という存在を、直接その人物とは縁のない者(と観客)が聞くということで、その死にまつわるエピソード”は”社会性”を持つ。
そのことに気づいた岡田が、何を題材にして能のフォーマットを使うか、その着眼点が本作の大きなカギになっている。そしてその言葉は社会批判とも言える鋭さをもっている。
まとめ
忘れ去られた者、負けてしまった者、志半ばで散った者、そうした敗者の視点から語られる言葉を「能」というフォーマットですくい上げる。それによって現代における社会のひずみを浮かび上がらせる内容だった。
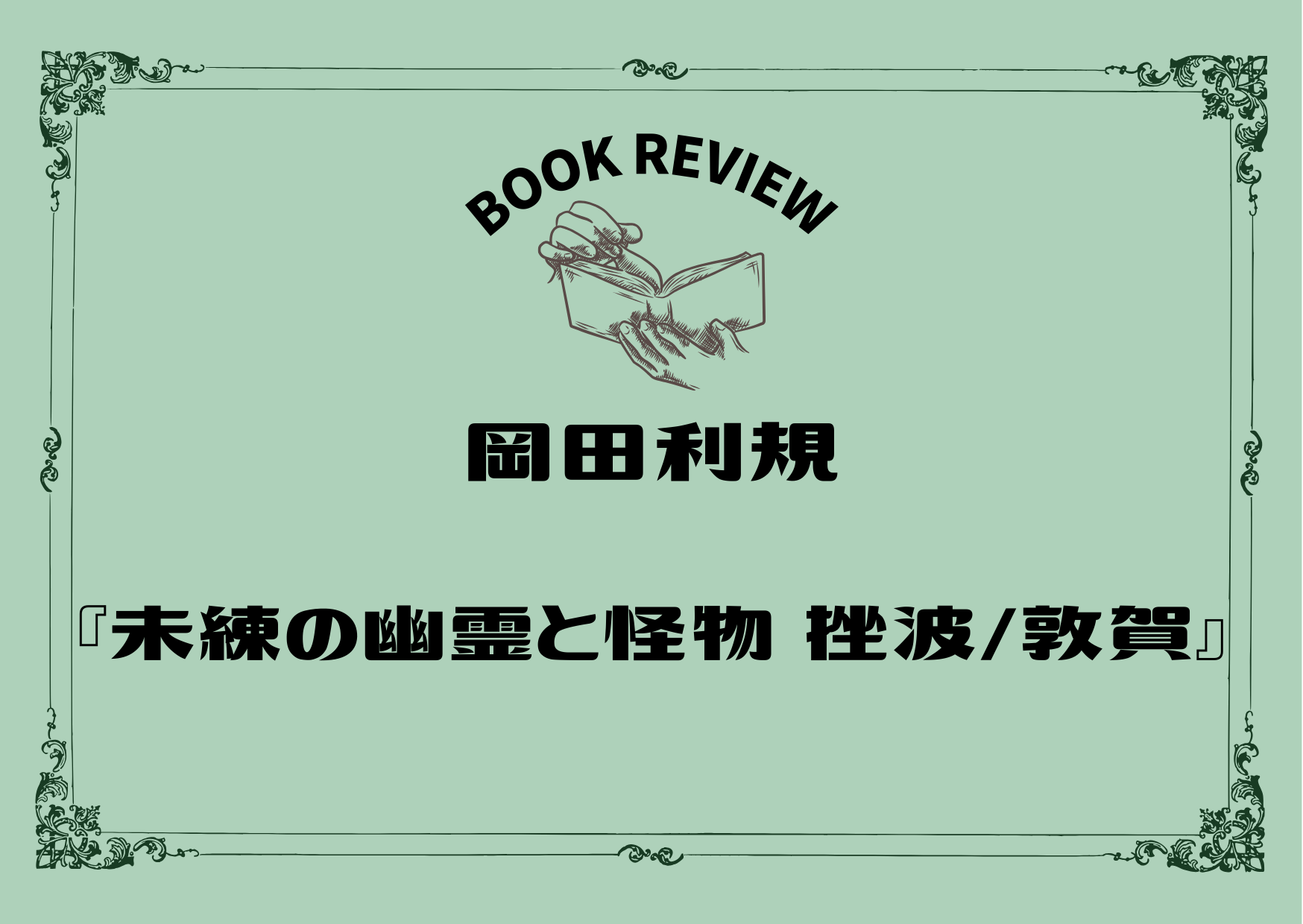


コメント