書家・美術家の篠田桃紅の随筆集『朱泥抄』は、書家らしい言葉への感度の高さを入り口に、日々の生活の営みの美しさを綴ったエッセイ。読むたびに澄みきった心で、1つ1つを丁寧に暮らしたくなる気にさせてくれる一冊だ。
書誌情報
書名:朱泥抄(しゅでいしょう)
著者:篠田桃紅
出版社:中央公論新社(中公文庫)
発行:2002年(初版)
ジャンル:随筆/美術/人生哲学
この本を手に取った理由
数年前に篠田桃紅の展覧会を観に行って、その作風と人生観に痺れるような衝撃を受けていた。そんな凛とした生き様の彼女に憧れてエッセイにようやく手を出した。
※篠田桃紅の展示についてのレビューはこちら
あらすじ(概要)
本書は、書家で美術家の篠田桃紅が、日々の思索や思い出、書への向き合い方を綴った随筆集。各章のタイトルは、「にんべん」「ごんべん」と、漢字の編(へん)になっており、その編にちなむ文章が綴られる。風にそよぐ柳のような、しなやかで無駄のない文章で、桃紅の凛とした美学が静かに響く。
印象に残ったことばと感想
様子がいい
江戸っ子の人と話をしていると「あのひとは様子がいい」などという言葉遣いを聞くが、高い美意識に裏打ちされた言い方だと思う
〈様子がいい〉という言葉は、姿かたちなど外見的なことだけではなく、佇まい、ものの言い方など含めて、それらが分断されず、さらに様々な要素を相まって、見る人に与える感覚を指す。見た目を取り繕うような「美」は張りぼてであることを喝破するような鋭さだ。私自身も周囲から「様子がいい」人でありたいと思った。
また、同じ章の中でプラスチックのものなど受け付けないという話が書かれており、影響を受けやすい私はすぐさま家中の(安物の)プラスチックを処分した(笑)。さすがに全てのプラスチックを家から排除することはできないが、自分がちゃんと見定めて買ったものではないプラスチックの籠などは、なるべく断捨離をするなどして整理していった。
顫音(せんおん)
海屋の書も、若い私の心には、何か未知の生を伝える顫音のようであった。
『朱泥抄』「幼きより」より引用(太字は筆者)
この頃よく岐阜へ行くが、金華山に対(むか)って、長良川の畔に立つと、川水の音につれて、あの「金碧」の顫音が聞こえるようでなつかしい。
本書を読んでいると、知らなかった言葉に度々遭遇する。その中でも特に印象的だったのが「顫音」だ。意味は音楽用語の「トリル(=2音を高速で連続して繰り替えす技法)」なのだが、その言葉の使い方が美しい。「未知の生を伝える顫音」、微かな心の揺れを音楽のトリルになぞらえる。
ちなみに顫音をネットの辞書で調べた時に出た用例に、高村光太郎の『道程』で「モナ・リザは歩み去れり かの不思議なる微笑に銀のごとき顫音を加えて」という一節が紹介されており、この使い方も美しい。
現代の私がこんな言い回しをしたら気障にしかならないが、こうした言葉が自然と使えて、それがしっくりくる人になりたいと思わずにはいられない。
この本をおすすめしたい人
- エッセイを書いてみたいと思っている人
- 「芸術」「日本の美」「言葉」に関心がある人
- 女性としての生き方に、迷いや悩みがある人
- 丁寧な暮らしや、美意識を高めたいと思っている人
まとめ
『朱泥抄』は、淡々とした文章の中に、深い静けさと強い意志が流れている。読むたびに、自分の中の「余白」が洗われて、自分自身の感性の網の目がより細やかになっていく感覚を覚えることだろう。
日々の喧騒から少し距離を置き、綴られている言葉1つ1つを味わいたくなる。
1人の女性として、美しくしなやかに生きる姿勢、自然の移ろいや煌めきを感じ取る感性を磨くことができるだろう。
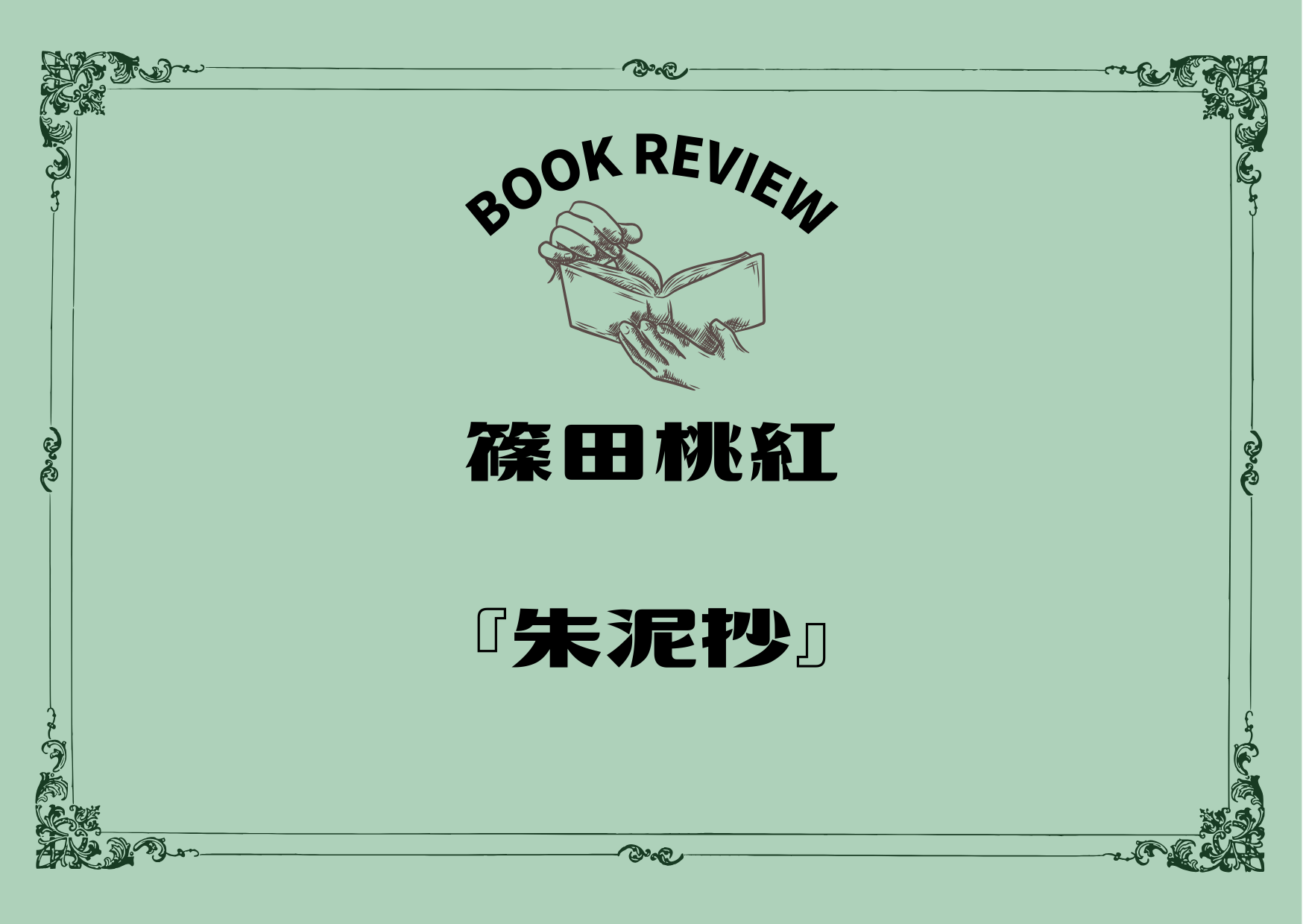

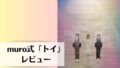
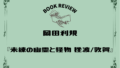
コメント