2023年12月6日、赤坂の草月ホールにて舞台『ある都市の死』が開幕した。推しであるs**t kingzのshojiとOguriによる二人芝居は2019年、2021年の『My freiend Jekyll』に続き3度目。前作に感動した身としては今回の作品も情報公開から期待に胸を膨らませていた。
今回は東京公演を3回鑑賞した。長文になるがぜひご一読頂ければ(全部で1万文字あります)。
『ある都市の死』概要
舞台『ある都市の死』は、演出家・瀬戸山美咲、s**t kingzのshoji(持田将史)とOguri(小栗基裕)が、ジャズピアニスト・小曽根真を迎えて、映画『戦場のピアニスト』でも描かれたピアニスト・ウワディスワフ・シュピルマンの戦争中の体験を描いた作品だ。
原作となったのは、以下の3冊。まずは、シュピルマン自身が書き、映画にもなった『戦場のピアニスト』。実は本作のオリジナルのタイトルが『ある都市の死』なのだ。
そして、シュピルマンの息子であるクリストファー・W.A. スピルマン氏による『シュピルマンの時計』。
そして戦場でシュピルマンを助けたドイツ人将校であるホーゼンフェルトの生涯についてまとめられた『「戦場のピアニスト」を救ったドイツ国防軍将校:ヴィルム・ホーゼンフェルトの生涯』。
これらの原作を基に、シュピルマンを持田将史(ピアノ演奏は小曽根真)、息子のクリストファー、ドイツ人将校・ホーゼンフェルトをはじめ、シュピルマンの周囲の人物を小栗基裕が演じるという、2人のダンサー&1人のピアニストという構成の芝居となる。
初日(12/6)の感想
東京公演初日の12月6日。この日は午前中に映画『戦場のピアニスト』を観た。本当は、初見は一切予習をせずに見て、私にとっての千穐楽である9日の夜公演までに映画ないしは原作で復習して9日の公演に臨むのが理想だったのだが、諸々の都合でその時間を取ることが難しくなったため、急遽初日の前に見ることにした。
結果としてはメリット、デメリット半々だった。当時の戦局を押さえることができたので、舞台でも史実の理解が追い付かないということはなくスムーズに見ることができた。一方で、終始映画のシーンが思い出されて「映画のあのシーンね」と、舞台に映画の光景を投影してしまった。これについては、もう映画のシーンを思い浮かべる必要がない2回目、3回目の鑑賞時の方が舞台そのものに集中できたので、複数回チケットを取っておいて良かった。
初日の感想は、小曽根さんのピアノと2人のダンス・芝居の息がぴったりで「これは一体どこがどう即興なのか?」と疑わずにはいられないほどだった。この日一番泣きそうになったのが、シュピルマン以外の家族全員が強制収容所へと送られた後、1人残されたシュピルマンが街中(舞台奥、雑然と置かれた家具が照明の効果によって瓦礫となった街中の光景となる)で呆然と立ち尽くすシーンだった。インタビューでshojiさんが「稽古の時、小曽根さんが弾くと街の景色が立ち上がった」というコメントをしており、実はその話をちょっと眉唾で読んでいた(とまで言うと失礼だ)が、「インタビュー用にちょっと盛ってるでしょ?」と思っていたが、このシーンで一気にボルテージを上げて繰り出される演奏は、まさに「荒廃した街の姿」そのものだった。家具が照明の効果でシルエットとなり、それが荒れた街並みへと変わる演出と相まって、孤独と恐怖と絶望をシュピルマンに与えるようにそびえ立ち、襲い掛かるように立ちはだかる街の光景を、観客の我々もシュピルマンの背中越しに見た。
そして、shojiさんのシュピルマンが戦局が過酷になるにつれて、その視線が近視眼的(目先数十センチ程度の距離に焦点を当てたような)顔になって、そのいびつな顔が、戦時下の極限状態の姿だと思うととにかく辛かった。ホーゼンフェルトに見つかりピアノを引くように促されて、久しぶりにピアノを弾く喜びを表現するダンスシーンで、shojiさんらしいダンスの動きを見て「あっ、良かった。目の前にいる人はちゃんとshojiさんだ」と安心するくらい、それまでのシュピルマンの姿が辛かった。
Oguriさん演じるホーゼンフェルトに関しては、「恥ずかしい!」という台詞に正直驚いた。映画ではホーゼンフェルトは、シュピルマンに対して優しく接するけれども自分の考えや感情を述べるようなシーンはなく、それが立場上慣れ合うことはできない者同士のギリギリの接し方としてしっくりきていたので、舞台のホーゼンフェルトがこんなに人間的であることに驚いた。(ラストのOguriさんがソロで踊るシーンは、床に寝そべっている時間が多く、私のこの日の座席からは寝そべってしまうと95%は見えなかったのでそれが残念。)
今回初めて小曽根さんの音楽を聴くことができたが、激しい中にも深みがあって、それが舞台全体を、2人の溢れる感情や、戦争という重いテーマ、それらを包み込んでくれる懐の深さがあって、「音楽に乗せてダンスと芝居をする」というより、小曽根さんの音楽が2人の芝居やダンスを受け止める器のように感じた。観客の方に向って外へ放出するベクトルの2人の感情に対して、舞台の中央で「作品」としてのぐっと引き締める、扇の”要”のような印象を受けた。
そう思っていると、終演後のカーテンコールでは、小曽根さんが優しい笑顔で2人を迎えて、それぞれの肩(背中)に手を添える姿が、父と2人の息子のような感じで、この重たいテーマを2人が向き合うにあたって、ピアニストという役割以上に、小曽根さんの人柄や見識の深さが2人の支えになっていたんだろうなと勝手に感じた。
まず3人でお辞儀をしてはけた後、アンコールでは1人1人が登場。そして一言挨拶する流れとなったのだが、Oguriさんが茫然としていて、現実世界に戻ってこれていない感じだった。その様子からも2人がどれだけこの重いテーマに愚直に向き合い続けてきたが感じられた。
2日目(12/8公演)の感想
本来は鑑賞する予定はなかったが、急遽8日の終演後に座談会が行われることになったため、追加で購入した。(ちなみに席はE列2番と下手側で、舞台下手側の奥側は完全に見切れてしまった。この設計なら両サイドはランクを落としてほしかった。あるいはリピーター割引をするなら、空席を正規料金の購入者に座席変更してリピーターをサイドにするなどしてほしかった)
2回目で、ようやく何がどう即興なのかを理解した。座談会でも小曽根さんがおっしゃったように、この日の公演は「攻めた演奏」をしていた。確かにそれぞれのシーンの演奏が、初日よりもアグレッシブな感じだった。私のザルな耳とポンコツな記憶力では「大きくちがう」という印象ではないのだが、全体的に、演奏の間合いや弾き出すきっかけなどが初日よりも”ズラシてる”感じがして、その「いつ何がどう来るか分からない」という緊張感が高かったように思う。
2回目の鑑賞とあって、私の中でも作品に対する解像度が上がった(つもりな)ので、この時点での私の解釈をまとめる。
まず冒頭の演奏、私はこれは「シュピルマンの人生」を総括的に表現していると思う。別の言い方をすれば、『ある都市の死』を屋根裏から見つける前の息子・クリストファー(に代表される世間一般の人々の認識にある)「ピアニスト、シュピルマンの人生」だ。苦しい時代を生き延びて、ピアニストとしてその才能を発揮させ、家族にも恵まれたシュピルマン、そんな風に周りからは見えていたかもしれない。不穏な旋律から次第に聞き心地のよい調べとなる演奏は、他者から見たシュピルマンの姿、あるいは彼自身がそうでありたいと必死にふるまっていたのか、理論武装ならぬ「音楽武装」しているような、美しいけど他者と何か一線を引くような哀しさをまとう音色だった。
そして、ラストにクリストファーが舞台上に並べる椅子6脚。これは戦争で死んでいった家族(シュピルマンの父、母、2人の姉、弟、そしてシュピルマンを救ったホーゼンフェルト)。ラストのノクターンは彼らへのレクイエムだ。
※椅子についてはシットキングスのファンサイト「062」内の記事で、椅子はシュピルマンも含めた家族の象徴として使われると説明されていたので、私の上記の解釈は公式とは違うことになるのだが、この日の私はそう感じたので、そのまま記しておく。(即興ものだし、作品の解釈はそれぞれなので「正しい/間違い」とは言わず「公式とは違う」と言う(意地です笑))
また今回の舞台のタイトルを『ある都市の死』としたことの意義を大きく感じた。『戦場のピアニスト』とした方が興行的には分かりやすいはずだ。しかしあえてそうしなかったのは、上演台本・演出の瀬戸山美咲さんをはじめ、shojiさん、Oguriさん、小曽根さん、この4人が共通して持っていた「シュピルマンの経験を”1人のユダヤ人ピアニストの特別な人生”として完結させない」という強い意志だと思う。例えば、映画がそうであるように、息子のクリストファーが登場しなくてもこの物語は語ることが出きるし、終戦後に捕虜のまま亡くなったホーゼンフェルトについては(おそらく残された資料がシュピルマンに比べたら限られているためだろう)創作物としての”ドラマ性”がある訳ではない。しかし、息子の存在が、過去の戦争を今の時代と地続きにするための橋渡し役となり、ホーゼンフェルトの人生を語ることは、戦争をどちらかの側からだけで語る危険を回避する。だからこそ本作は『ある都市の死』でなければいけないのだ。
そしてそう思うと、劇中の度肝を抜くほどの膨大な量の年月日と固有名詞(人物名、町や通りの名前)の意味も腑に落ちる。おそらく、あそこまで具体的な名前や数字を入れなくても言いたいことは伝わるし、説明的すぎるとその分芝居としてのリズムや見る側のストレスの問題も出てくる。そんなことは百も承知の上であれだけの情報をつぶさに入れているのは「失われていった人、町、文化、歴史」を言葉にして、それが”かつて存在していたこと”を留めようとする思いの現れなのだと感じた(もちろん劇中で登場するすべての人物が戦争で死んだわけではないだろうが、全ての人が戦争という人類史上一番愚かな行為による被害者という意味でここでは”失われていった人”に含める)。
息子のクリストファーが舞台で狂言回しの役割を担っているが、少し飛躍した言い方だが、シュピルマンでさえそうなのかもしれない。彼の人生を語るようでいて、本当に語っているのは、人生という舞台の幕を強制的に閉じることとなった「舞台にいない人々」であり、それこそつまり「都市の死」なのだ。だからシュピルマンが最後に弾く(踊る)ノクターンは、彼らに向けてのレクイエムなのだ。
ちなみに、座談会で「今回瀬戸山さんの肩書が脚本ではなく上演台本となっているのは、原作3冊にある言葉にほとんど忠実で、新たに脚色してはいない」ということが説明されており、(まだ原作は読めていないのだが)私が初日に感じたホーゼンフェルトの「恥ずかしい!」という台詞や人間的な一面を見せているのも、おそらく原作の中でそうした言葉があった、あるいは残された言葉から彼の人となりが造形できたのだろう。この疑問が解消できただけでも座談会に参加できてよかった。
3日目(12/9夜公演)の感想
3回目の鑑賞となる12月9日。前日の2回目の鑑賞で上記のような考えにいたり、その解釈に確信を持ちたいがゆえに、ちょっとしたワクワク感を抱いて鑑賞に臨んだ。
しかし、自分の解釈は間違っていないのではないかという期待は、冒頭の演奏で見事に打ち砕かれた。
「全っ然ちがう!!!!!!ナニコレ???初っ端からこんな飛ばしていいの?」
今回は最前列センターという神席だったのだが、その最前列であまりの違いにのけぞりそうになった。1回目と2回目の公演の差はそれほど大きく感じなかったが、この3日目の演奏は私のザルのような耳とポンコツ記憶力でもはっきりと分かるくらいにまるで違う。私の想定ではここはそんな感じじゃない!!(笑)
もうね、小曽根さんに「昨日の解釈で今日の舞台を観るな!」と頬をビンタされた心地ですわ。即興とはこういうことだ、と教えていただきました。かっこよすぎます。
3回この舞台を観て、このオープニングの演奏について私なりのイメージを言うなら、
・初日の演奏は「正統派」もしくは「基準/完成形」
・2日目(12/8)の演奏は「挑戦的」「先鋭的」
・3日目(12/9夜)の演奏は「反逆的」「異端」
9日は昼夜2公演ということもあって、3人とも昼公演の火照りがまだ体に残っていたのか、序盤から感情がすごく乗りやすくなっているように感じた(最前列で表情が一番よく見えたからかもしれないが)。後半ではshojiさんが、それまでは声を張って語っていた台詞を呟くように言ったりと(おそらく昼公演から)蓄積されていく疲労が、そのまま戦争状態で疲弊していくシュピルマンの状態になり、2回目までに受けたシュピルマンの姿とまた異なる印象を受けた。
それゆえに3回見て、3回とも全然違うところで感動した。初日は上述のように襲い掛かる街の姿の表現に胸を打ち、シュピルマンがどんどん荒んでいく姿、ホーゼンフェルトのその後の運命に切なくなったが、3日目でもっとも胸を打ったのは、家族が強制収容所に送られて以降、ゲットーからも逃亡して1人部屋にこもる中で、空想で演奏するシーン。小曽根さんが光の中で美しい旋律を奏でる一方で、shoji演じるシュピルマンは弾くことができない現実に泣き、震える。最前列で2人がちょうどシンクロして見える位置で、shojiさんの横顔(表情)もはっきり見ることができたので、この理想と現実がどんどん乖離していく光景が強烈に響いた。
そして、ホーゼンフェルトに見つかる時のシーン。初日、2回目でもこの時のシュピルマンの極限状態は見ていて苦しかったのだが、最前列でその姿を目の当たりにすると、荒んでいるというレベルじゃなく「獣みたい」と思った。戦前は紳士的に優雅にふるまっていたであろうピアニストが、飢えた獣になった。
実はこの時のホーゼンフェルトの「あなたは何をして暮らしているのですか?」という台詞が、2回目までの時は正直「ちょっとキザな言い回し(芝居がかった台詞)だな」と感じていた。なんというか、その後の「私はピアニストです」という言葉につなげるために用意された感じがしていた。しかし、3回目でようやくしっくり来た。ホーゼンフェルトはシュピルマンを憐れんでいるのは、戦争で極限状態になっているという表面的なことではなく、ユダヤ人という理由だけで家も財産も家族も奪われ、砲撃が行われると忠告しても「どうぞ好きにしてください」と自分の命を守ることすら放棄して(某漫画風に言えば「生殺与奪の権を他人に握らせ」て)、その「人間としての尊厳が失われている」状態なのだ。
だからその尊厳を取り戻すためにもあの質問は必要だった。彼自身が忘れかけてた(諦めていた)ピアニストであることを思い出させるために。シュピルマンが”人”になるために必要なのはパンではない。音楽なのだ。ノクターンを引きながら次第に軽やかになるshojiさんのダンスはその尊厳を取り戻す姿だった。
ラストの演奏も今回が一番激しかった。小曽根さんはまだ何かと闘うようだった。
この日の終演後はアンコールが3回だったかな。最後はスタンディングオベーションとなった。朗らかに笑い、こちらを讃えるような小曽根さんの表情、万感の思いの2人にあらんかぎりの拍手を送った。

どこにも入れられる余地がなかったのでここで言いますが、「不貞腐れた小猫ちゃん」を演じる小曽根さんのプイっとそっぽを向く背中が可愛すぎて、そこのシーンが好きすぎます!そして世界的ジャズピアニストにたどたどしい演奏をさせるとはある意味他では絶対に見られない貴重な演奏!(笑)
おわりに
まずは、思い出せるままに書き綴ったこの長文を最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございます。前作『My freiend Jekyll』に心を鷲掴みにされた者としては、瀬戸山×shoji×Ogruiのタッグで作られる舞台が本当に刺さる!!これからもこの3人(もしかしたら+α)の舞台を観続けたい。
そして、この舞台を観たからには「感動した」では終わらせず、今まさに起きている問題について、まずは知ることから始めようと思った。ロシアとウクライナの問題で実感したが、たとえ誰もが「戦争は良くないことだ」と分かっていても、一度始まってしまったら終わらせることは難しい。そして今まさにイスラエルとパレスチナの問題も深刻になっている。今すぐに私が「世界を変える」何かをすることはできないが、自分自身が「知り、学び、考える」。そのことは今からでも変えることができる。そこから始めよう。
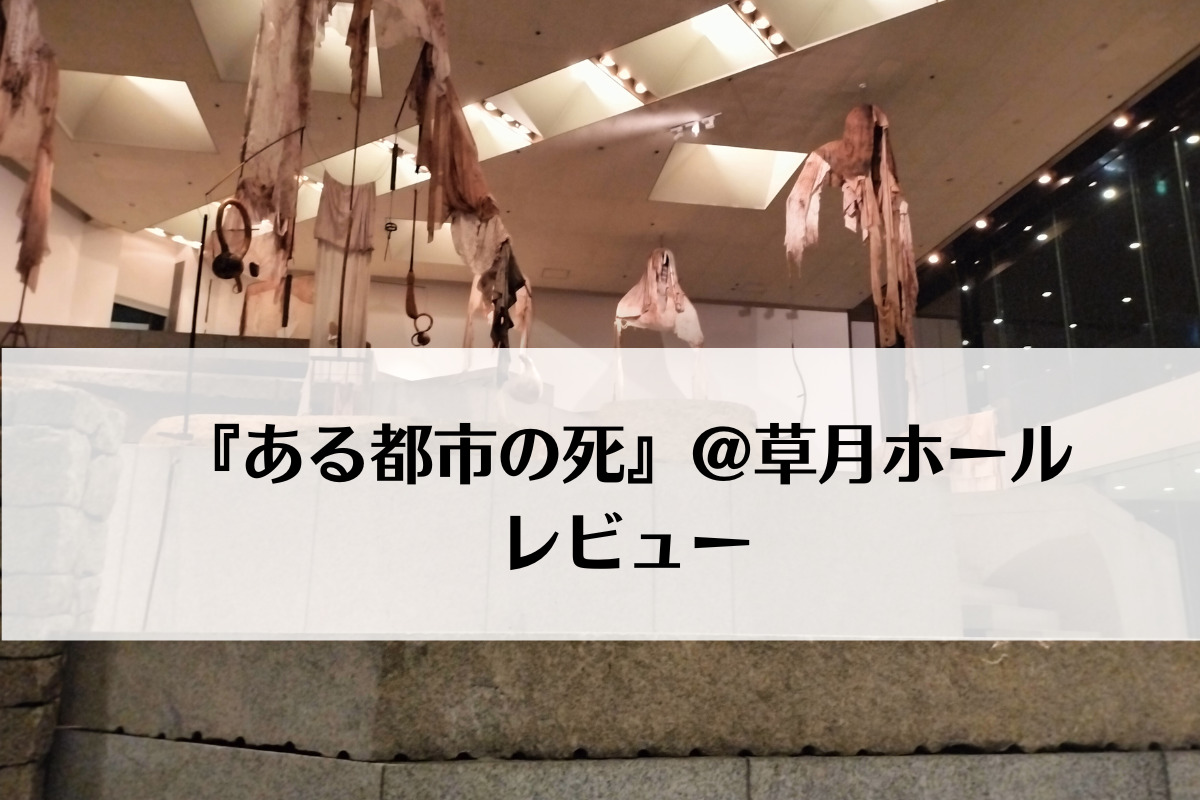


コメント