2023年7月24日(月)、高田馬場の早稲田松竹で甫木本空監督の「はだかのゆめ」の上映とトークショーが開催された。
6月にBialystocks(ビアリストックス)のライブに行って、そこからボーカルの甫木本空さんが映画監督もしていることを知り、見たいと思っていた作品だった。その時は既に上映は終わっていて見る機会がないのかと残念に思っていた矢先だったので、今回の上映は僥倖とばかりに、トークショーに合わせてチケットを購入した。
そして、人生で初めての早稲田松竹に足を踏み入れた。
映画「はだかのゆめ」
「はだかのゆめ」は、甫木本空の2作目となる映画作品。母親の死という監督自身の経験を基にしており、主人公のノロは、母と祖父と一緒に暮らしているが、余命幾ばくも無い母親の運命を受け止めきれずにいる。できることをきちんと過ごす日々を生きる母親、生きるために働き続ける祖父、運命に向き合いきれずにいる息子…それぞれの思いを抱えて共に生き、そして死んでいき、それを見つめた3世代の家族の物語だ。

私は前情報として、①監督自身の家族の体験(母親の死)がベースになっている、②実際の祖父が映画にも登場し、舞台も監督の両親の故郷の四万十で行われた、ということは踏まえた上で観に行きました。
作品レビュー
トークショーのレポートの前に、簡単に私自身の感想をまとめておきたい。
最初の冒頭は、唐突に映像が切り替わり、音もブツっと切れる展開が続き、シーンとシーンのつながりが理解できずに困惑の連続だった。親子3世代の物語、母親の死がテーマという前情報を持っていたから、何とかそれを手掛かりに自分の中で解釈しようとしたが、まったく何の予備知識がない場合、ちゃんと汲み取れたかどうかは心許ない。
それでも不思議と見ていて居心地が悪くならなかったのは、主人公、母親、祖父、おんちゃんという登場人物それぞれのまなざしが優しく、また彼らに向けるカメラアングル(つまりは監督のまなざし)が丁寧だったからだったように思う。何をもって”丁寧”と言えるのか、その理由が上手く説明できないのだが、どこにも突き放すような視線がなかった。
四万十町の自然とその中で暮らす3人+おんちゃんだが、その田舎のシーンが「良くも悪くもまさに田舎」という感じだった。よく言えば雄大、悪く言えば辺鄙な四万十の町を、どちらに偏るでもなく、ただ”ある”ように映していると感じた。変に「田舎で家族と暮らす」ことを美しく描いてはおらず、今もどこかの地方で起こっているだろう「この世界の片隅」としての田舎の描写に説得力があった。
それは、私自身が地方の出身で、地方の暮らしの「穏やかさ」も「行き場のなさ」も知っているつもりだからだろう。10代の頃の多感だった時に感じる田舎での「生と死」「家族との距離感」を思い出した。優しさが近すぎて、上手く距離を取れない感じ。でも、居る。互いにその”気配”だけは感じている。家族だからこそ踏み込めないでいる、そのことに甘えていつまでも向き合えない、その感じが身に染みた。
途中、「あれ?もしかしてノロの方が死んでいるとか??」と混乱することが多かった。そういう混乱さえ起こっても良いと敢えてしている。パンフレットのオリジナル・シナリオを読んでも、そういう風に解釈できなくはない気がして自分の理解が正解なのか不安になる。パンフレットの保坂氏の寄稿の中で「この映画は接続詞で繋がれていない」という表現がまさにその通りだ。時系列にそって物語は時系列に沿って展開しているだろうが、すべてが過去の「回想」のようでもあるし、現実と空想(心象風景や誰かにとっての回想)が交互に起きているようでもある。
見終わった直後は咀嚼できずにいた部分も多かった(今も混乱している)が、二日経ってみて今自分の心に残る映像は、川のシーンだ。火降り漁の篝火のシーンと、ノロが母親へ渡すつもりだったプレゼントを入れた紙袋を沈下橋の上から流すシーン。今振り返ると、まるで精霊流しのイメージを重ねているようにも思えてきた。
そうやって思いを馳せると、あの土地でずっと生き、今も確かに生き続けてる者としての祖父はずっと畑仕事など「土(=大地)」の上にいて、ノロは船の上や川岸など、水辺のシーンが多かったように思う。精神的な安定/不安定、生/死の対比が土と水に表されているのかもしれない。
明確な起承転結が提示される”見やすい”映画に慣れた私には難解で混乱の連続であったが、身近な誰かの死に直面した時、その死にゆく相手との物語は、そんなにきれいに筋道立てて語れるほど簡単ではないだろう。私がこの映画の手法で感じた”混乱”は、監督自身の実体験として、そして劇中のノロの体験として感じた”死にゆく母”という事実に向き合うことへの混乱の追体験と言えるかもしれない。
甫木本空(監督)×廣瀬純(映画評論家)トークショー

今回のレイトショーでは、上映後に甫木本監督と映画評論家の廣瀬純氏によるトークショーが開催された。このお二人の話のおかげで、かなり作品の解像度が上がった。いろいろなキーワードや制作の経緯など話が広がったが、今回はその中でも私が特に興味深く感じた点をまとめたい。

「映像の切断(切り替えし)」と「音の連続」で紡ぐ
まず、廣瀬さんから本作の特徴として「切断(=切り替えしの多用)」と「登場人物が1つの画面の中で共存しない」点が挙げられた。主人公(ノロ)、母親、祖父の3人が同じ家に住む(同じ空間を共有している)にもかかわらず、決して1つの画面の中に共存することはない。
確かにまず切り返しの多さに気づいた。特に冒頭は「ここから何かが始まるかな」と期待した瞬間にシーンが切り替わるということが何度か続き、その都度意識がリセットされる「もどかしさ」、一歩進んでは半歩戻る感じを味わった。しかし、振り返ればその「細切れ」感が、それぞれの登場人物の関係というか距離感の遠さを体験することになる。
そして、おんちゃん(前野健太)以外は決して一つの画面に収まらない。私はこの手法にかなり翻弄された。同じ時空間にいるつもりで見ていいのか全然分からなかった(笑)。「これは回想?それとも主人公の夢?心象風景?」と色々考えてしまったし、「生きてる者が死んでいて、死んでる者が生きているような」という台詞では「あれ??もしかしてノロの方が死んでたとか???」とかまで思ってしまった。
思い返してみれば、そのくらい主人公・ノロは母親の死を受け止めるまで存在感が希薄で、死にゆく運命にある母親の方が地に足がついていて、祖父はぶれることなく確固として「生きている」。その3つの佇まいが明確に表現されていた。
一番驚いたのは、終始ずっと”死んでいるように”生きていたノロが、最後にようやく母親の死を受け止め、母親が日々の出来事や思いを書き綴っていたノートに向き合ってからラストのシーン。劇的な変化や行動があるわけではないのに、確かに「変わっている」ことが伝わって来た。あのセリフも少なく行動も少ない中で、眼が確かに変わっていて、それを演じわける青木柚さんの演技力に脱帽した。
そして甫木本監督の説明で初めて気づいたことは、映像は意識的に切断(切り返し)と共存しない画を作る一方で、音ではシーンとシーンをつなぐように入れて「連続」させていて、「画が紡ぐ物語」の一方で「音が紡ぐ物語」を意識していたとのこと。正直、音に関しては最初のブツっと切断される展開の印象が強く、「音が紡ぐ」という部分は、コーヒーミルを挽く音がシーンが変わっても続いてく箇所くらいしか記憶になかったので、これはもう一度見て確かめたいと思った。

「祖父」の存在
本作の特徴の一つが、監督の実の祖父である甫木本尊英さんが、祖父役として登場していることだろう。しかし祖父”役”と言っても、お祖父さんに演技をしてもらっている訳ではない。お祖父さんはあくまでお祖父さんとして、そこで暮らしているのだ。そのお祖父さんに対して、役者が演技をする。
こんな「虚」と「実」の綯い交ぜの仕方があったのか!!と目から鱗だった。正直見るまで「どういうこと?本当に成立するの?」と思っていた。しかし実際に見てみれば、この「祖父」の存在が、現実を受け止めきれずに、どこかこの世にいないようなノロ、彼岸に行く運命を抱えた母(祖父から見れば娘)という、ふわっとしている2人の魂をつなぎとめる存在であったように思う。
トークショーで監督は、映画の中でのお祖父さんの役割(位置付け)を「反復する行為をする者」と語っていた。その反復する行為こそ「生きる」ことの象徴でもあるのだろう。
お祖父さんの存在については、パンフレットの青木柚さんのインタビューが興味深い。事前に監督から「こう聞けばおじいちゃんは話し出すから」というアドバイスがあり、そのようにしたのだが、言葉が届かない。その時に、普段は役者同士で「この台詞を言えば、相手はこう返す」という決まりの中で、”言葉が通じている”ように見えてただけで、役者ではない人と話したら伝わっていないってことかと感じたそう。
芝居をしないお祖父さんから、芝居における「リアリティ」とは何かを突きつけられる。このエピソードを読んだ時、とてつもなく革新的なことが静かに行われていたのだと気づいた。
デザインされた映画とは
トークショーの中で少し触れられた話題が「デザインされた映画とは」という話だった。これは廣瀬氏がもともと持っている「デザインされた映画とは何か」という見解で、要は普通映画を撮っているとどうしても「人物至上主義」の構図やカットになりがちだが、「デザインされた映画」とは背景の建物や小道具やらといった人物以外のものが構図やカットの大きな要素となって、人物がそれらと等価となる、ということだ。
その例が小津安二郎だろう。思い出せば確かに、主要な登場人物たちも構築的な構図の中に収まり、「人物のために画がある」のではなく「画のために人物がいる」という主従関係になっている。
その他にも登場人物がそれぞれ持つ「道具」や、「窓」の役割、「見る者/見られる者の関係」などについて語られており、それらも実に面白かった。話の最中「そのシーンもう一度見たい!確かめたい」と何度も思ってしまった。
最後に
トークショーの後には、監督のサイン会も実施されました!ペンの色が銀色なのも作品や監督の佇まいに合っていて良いなと思った。
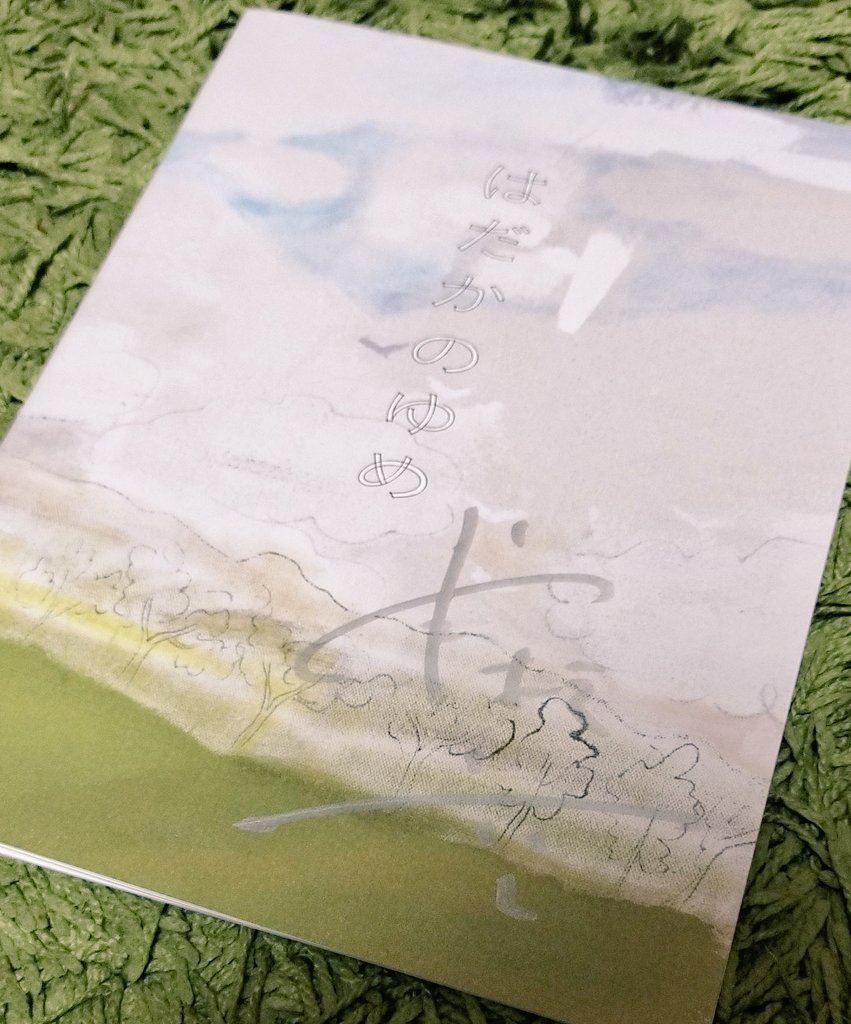
映画のエンディングで流れる「はだかのゆめ」は、ノロの、監督の、母親へ、死にゆく者へ捧げる言葉だ。無邪気で、無垢で、叶うことのない儚いその「ゆめ」は、きっと空に届いているだろう。
早稲田松竹に向かう道中で高田馬場駅で見た天使の羽のような雲。これはもう限りなく必然の偶然。

12月には高知県立美術館で個展開催
映像作家としての甫木本空の今後については、12月に高知県立美術館で個展が開催される。この展覧会も注目だ。
「甫木元 空 窓外(仮)」
場所:高知県立美術館
会期:2023年12月16日[土] – 2024年02月18日[日]
会場HP:https://moak.jp/event/exhibitions/post_499.html



コメント