s**t kingz(シッキン)の2022年9~11月の舞台『HELLO ROOMIES!!!』(『ハロルミ』)のリハーサルがまるで「文楽のようだ」と感じたこととから始まったこの考察。
前回は「人形」と「人形遣い(=シッキン)」の関係を中心に文楽との比較をしながら、シッキン&A子(『ハロルミ』で使用する人形)のパフォーマンスについて考えた。
続く今回は、そのパフォーマンスを観て感動した私たち観客の感動は、結局のところどういうことなのか、我々観客がA子をどのように見ていたのかという、「A子(人形)と観客」の関係を考えていきたい。
※前回からの続きという意味でタイトルに「文楽」を入れていますが、今回はそこまで文楽は関係してきません。
A子へ向ける眼差しー”小道具”から”共演者”へー
A子が私たちファンの前に姿を現したのは、決して6月2日の062感謝祭(シッキンのファンサイトイベント)が最初ではない。随分と前から舞台のチラシにも登場し、youtubeで公開されているティザー動画にもしっかり”主役”として存在している。
しかも、4~5月に行われたトークショーの会場では、実際のA子が物販スペースにも展示されており、我々ファンも直接見ることができた。

私たちは既にA子と直接対面しているのに、A子に向ける愛着は、062感謝祭での配信後の方が大きかった。その証拠に、配信後の私のtwitterのタイムラインでは、アイコンをA子の顔にしたり、上の写真でA子が着ているスーツの柄をアイコンの背景にしたりと明らかにファンの間でA子への愛が高まった(私自身もA子を中心にしたイラストを描いた)。
これはどういう変化なのかと考えた時に、なるほど、トークショーの時のA子の様子を、私は「物販スペースにも展示され」たと言った。そうだ、この時のA子はまだ私(観客)にとっては「人形」という「物」に過ぎず、キャッキャッと写真は撮るが、その眼差しはHMVで度々行われるシッキンの衣裳展示の時とそれと変わらない。彼らの過去の舞台『The Library』の本のように、「舞台を象徴する小道具の1つ」という認識であり、トークショーの段階ではそうした「シッキンゆかりの小道具を生で見た」喜びでしかなかったのだ。
しかし、配信されたリハではA子はシャツにジャージという練習着を着て、シッキンメンバーによってストレッチをしたり、人間さながらの(とてもダンス初心者という設定とは思えない)センスある音の取り方で、どんどんと踊りを覚えていく。メンバーのA子の扱い方も、最初はぎこちなかったが次第に慣れていき、徐々にその動きが滑らかに、より自然になっていく。
A子の動きが滑らかになればなる程、シッキンの「人形遣い」としての動きは気にならなくなる。そうなった時、我々はA子はもはや「小道具」とは見ていない。シッキンと共に踊り、舞台を作る「共演者」になったのだ。
そして、その「共演者」とは、実は「私(観客)」なのだ。
エンプティネス ー観客自身を投影する器としてのA子ー
いきなり「共演者=私(観客)」と言われて「??」と思われたかもしれない。この飛躍したように見える結論を考える上で紹介したい本がある。原研哉の『白』という本だ。
本書はグラフィックデザイナーである原研哉氏が「白」という色の機能についてデザイナーの観点から、「白」という色どのような存在としてそこに在るのか、他者とのコミュニケーションであるデザインの中でどのように機能しているのかを紐解いている。
「空(うつ)/エンプティネス」だからこそ全てを包容する
私が本書の中でもっとも感銘を受けたのがこの「空(うつ)/エンプティネス」という概念だ。少し長くなるが、本書の一部を引用する。
白は時に「空白」を意味する。色彩の不在としての白の概念は、そのまま不在性そのものの象徴へと発展する。しかしこの空白は、「無」や「エネルギーの不在」ではなく、むしろ未来に充実した中身が満たされるべき「機前の可能性」として示される場合が多く、そのような白の運用はコミュニケーションに強い力を生み出す。空っぽの器には何も入っていないが、これを無価値と見ず、何かが入る「予兆」と見立てる創造性がエンプティネス力を与える。このような「空白」あるいは「エンプティネス」のコミュニケーションにおける力と、白は強く結びついている。
原研哉『白』(中央公論新社)
要は空っぽであるからこそ、全てを受け入れることができる、ということである。神社の「社(=屋代)」は何もない空間の四方を囲い、それによって区切られた「空っぽ」の空間こそ、神社の中枢となる。何もないのに。それは「何もない」のではなく「いずれそこに神が宿る可能性がある」のだ。それ故に神聖であり、求心力、また時間を超えた普遍性を持つ。
その他の例として日本の国旗の「日の丸」が挙げられている。”白い長方の中央に赤い丸”という極めてシンプルなこの図は、本来それ以上でもそれ以下でもない。しかし人はそこに別の意味を見出す。その図形を太陽と見る人もいれば、弁当箱に敷き詰められた白米の上の梅干しを思い出すかもしれない。天皇や帝国主義の思想の反映と見做す人もいるだろう。それによってもたらされた負の歴史が脳裏を掠める人もいるだろう。
しかし、どれが正解という事はない。どれも正解なのだ。思いたいように思うことができるという意味で、この図形は「エンプティネス」なのだ。1つ前の段落で私は日の丸に対して「人はそこに別の意味を見出す」と書いたが、正確に言えば見出しているのではない。その意味を日の丸の中という器の中に自分が思っていることを「投影」しているのだ。
そしてこの図形が極めてシンプル(=空っぽ)で「エンプティネス」としてのパワーが強いからこそ、日の丸は国旗として存在し続けている。これがもし、より具体的なモティーフがあれば歴史のどこかで、その時代の思想・情勢によって変更させられていただろう。
人形は”エンプティネス”な存在
このエンプティネスという概念を用いれば、A子という「人形」こそエンプティネスなのである。よく人気キャラクターやぬいぐるみの表情は無表情で、だからこそ見る人の気分によって楽しそうにも感じられたり、寂しそうにも感じられる、という話は耳にするだろう。その”無”表情こそエンプティネスだ。
日本の演劇で言えば、能における能面も同様であろう。無表情に見える能面が、舞台の上で物語の内容、囃子、舞が相まって、哀しそうにも見えれば嬉しそうに見える時もある。シテ(物語の主人公で、多くの場合能面を用いる)の技量と表現力によって、”無”表情の能面に”無限”の表情を表すことができるのだ。そしてそれは文楽の人形もまた同じだ。
A子の物語=”私”の物語
人形がエンプティネスであるからこそ、それを見る私たちは自分の感情を投影しやすい。そして今回の『ハロルミ』を考えてみよう。
映画監督になることを夢見るA子は、チャンスに恵まれず悶々とする日々を過ごしてきた。
思い通りに行かない人生、何もできずに過ぎていく時間。
日々積み重なる複雑な思いが、A子の心に”ゴミ”として溜まっていく。
すると、彼女の部屋もまた、ゴミで溢れていくのだった。
そんなある日、A子に映画監督としてデビューするチャンスが舞い込むが…
何を選び、心のゴミとどう向き合っていくのか。
A子とゴミ達、そして癖の強い仲間たちが繰り広げる、超踊る喜劇!!!
チラシのストーリーを書き起こしたのだが、冒頭3行、(映画監督はめざしてないけど)自分の事過ぎて危うくメンタルをやられるところだった…危ない危ない。
A子は29歳という設定らしい。日々の生活、これからの自分、働き出したからこそ感じる「どうすればいいのか、どうしたいのか…」という悩み、焦燥。こうした誰もが一度は抱えたことのある問題を軸に物語は展開されていく。
私はシッキンの無言芝居は『The Library』しか見ていないのだが、彼らの無言芝居は、常に「4人組」というクローズドな世界であり、観客はその物語を「どこかにいる男4人」の話として、つまり”他人事”として眺めていた構図であった。
しかし今回はA子という女性、しかも”エンプティネス”である人形の女性が登場することで、その物語は観客とっては、”私の物語”として捉えやすくなる。重要なのは、「私の境遇と近い人」というあくまでも他人事ではなく、人形に自分自身を投影しているので「私」の物語になるということなのだ。
A子は「共演者」であり、その共演者とは「私(観客)」であると言ったのは、そういう意味からだ。前回の記事で、近松門左衛門が心中物といったリアルタイムで起きた事件を作品にした時期から、文楽の人形がより写実的になり、表現が様式化されていくという話とも通じる気がしますね。
文楽も『ハロルミ』も、より「リアル」な問題を扱うからこそ、”エンプティネス”だけど”リアルに動く”人形が、観客に「自分事」のような没入感を与える。そしてその一方でその表現は、文楽で言えば「型」あるいは「様式美」と評される演出で、シッキンの場合はコメディタッチにすることで、生々し過ぎて生じる嫌悪感、あるいは題材とする問題の重さ(しんどさ)を軽減させる。

kazukiさんもインスタライブで、「これがコメディじゃなければやってたかどうかわからないテーマ」と言っていたが、コメディタッチにすることがシッキンの「型」ということなんでしょうね。そういう意味では『独裁者』のダンスが如何に彼らにとって「型破り」な手法で、彼らにそうさせる程の思いがあったことに今改めて思いを馳せてしまいます。
『独裁者』の考察を読み返したら、このチャップリンのスピーチもまた”エンプティネス”として機能しているという事になるな。そしてシッキンの表現力のふり幅‼
A子はなぜ29歳なのか
少しわき道にそれたが、ここまで書いて行く中でA子の「29歳」設定も絶妙だなと思った。最初にA子が29歳と知った時、30半ばの私は「けっ、人形とはいえ一緒に舞台に立つ”女性”は20代が良いか。そうかそうか。」「人生に悩むのが10代20代ばかりと思うなよ!30半ばで絶賛迷い中だコノヤロー‼」と荒んだ気持ち(それこそ心のゴミ)が溢れたが、このエンプティネスとしての機能に思い至ると、この設定が実にちょうどいいと思えてくる。
これがシッキンが30代だからといってA子の設定を30代にしてしまうと、10代には少し遠い存在になってしまって、エンプティネス(自身を投影する器)としての機能が弱まる。これはならないと分からない事の1つだと思うが、「大人って思っているほど大人じゃない」。だから実際は20代でも30代でもそれ以上でもまぁ悩む。そりゃそうだ、誰もが人生1回目なのだから。ただその事は経験しないと分からないため、10代にはまだイメージしにくい部分だろう。その10代においてもある程度イメージできる”大人”、「今の自分」にしろ「過去の自分」「未来の自分」にしろ、あらゆる世代の観客それぞれが「自分」を投影できる距離感が「29歳」なのではないだろうか。
もしこれでA子の設定が本番では10代とか20代前半になってたら、その時は「人形とはいえ”女性”は若い方が良いんだな」と思おう(笑)
おわりに
6月2日に感じた衝撃を言葉で整理するのに、中々時間がかかった。読んでくださった皆さん、本当にありがとうございます!!彼らのパフォーマンスの凄さを語り得た手応えはあるような、ないような…というところですが、多分、というか絶対に、本番の舞台では、私が言葉で捕まえたと思ったものはとっくにそこにはなく、さらに素晴らしいものを見せてくれると期待している。
最後は、拙文にお付き合いいただいた皆さんのお口直しに。
最後まで読んでいただきありがとうございます‼
もしよろしければ、下記ボタンのクリックで応援していただけると嬉しいです!
にほんブログ村



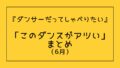

コメント